『東映版Keyのキセキ』序文の全文を公開します。
告知ですが、以前ブログでも触れていた東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』の合同評論同人誌を発刊しまして、現在BOOTHにて予約販売中です。
同人誌は完全受注生産で、11月末までの予約受付になっています。興味がある方はお見逃しなく…! という告知です。以下に本誌の序文を掲載させていただきます。
序文
本誌の目的は、いわゆる「東映版Key三部作」の作品群をとりあげ、その魅力や作品の持つ意義について語ることである。「東映版Key三部作」というのは、ゲームブランド・Keyの作品を原作に、東映アニメーションにより制作された以下の三作品を指す。
この企画が持ち上がった直接の契機としては、昨年2019年末に刊行されたKeyの歴史を解説する書籍『Keyの軌跡』(坂上秋成著、星海社新書)において東映アニメーション制作のアニメ版についてほぼ記述が割かれていなかったことがある。Keyのこれまでの総決算として位置付けられるこの書籍において、京都アニメーション版(以下、京アニ版)の『Kanon』『AIR』『CLANNAD』に主に記述が割かれる一方で、東映アニメーション版(以下、東映版)についてほぼ記述がないということには偏りを感じ、何かそれを補完するようなものが出せないか、という着想だ。
また、Keyは20周年の節目を迎えた2019年から2020年にかけて、20周年特設サイトでの総キャラクター人気投票「Key総選挙」や『Key20th MEMORIAL BOOK』の刊行、『神様になった日』の放送に合わせた「麻枝准研究所」の開設など、これまでの総決算としてとれるような企画を打ち出しており、Keyの歴史の中で東映版があぶれてしまっているのだとしたら、これを機にその再評価に繋がるものを打ち出すことは極めて有意義だろうと考えた。
そこで「見過ごされがちな『東映版Key三部作』について今一度振り返って再考すること」を目的に、様々な書き手に寄稿していただく合同評論同人誌の企画が始動した。様々な寄稿者の協力のもとでそれが成就し、形になったのがこの『東映版Keyのキセキ』である。
上記のような経緯はあるものの、強調しておきたいのは、本企画は京都アニメーション版や原作に対するカウンターを意図したものではないということである。東映版を支持するということは必ずしも京アニ版や原作を批判するということにならない。「京アニ版VS東映版」のような対立は、同じタイトルを二社がアニメ化したことによって事後的に作られたイメージでしかなく、そもそも両者は対立した位置づけにあるわけではない。あくまで、両者ともそれぞれに異なる特質を持っており、その中での東映版の価値を評価したいというのが一貫した立場だ。加えて、『Keyの軌跡』やその著者に対して敵対する意識もない。
ただし、東映版を正しく評価する上では、東映版および京アニ版に対して向けられるステレオタイプな見方に対し反発するということは必要になる。一つには「東映版は原作とは違うオリジナル、京アニ版は原作に忠実」といったものだ。
例えば、先ごろ刊行された『Key20th MEMORIAL BOOK』(KADOKAWA、2020年)の『Kanon』のページにはこう記載がある。
「東映アニメーションが2002年に、京都アニメーションが2006年に2度アニメ化。オリジナル展開の前者、原作を尊重の後者と魅力が異なる」
これは概ね我々の理解に近いまとめであり、限られた字数で両者の特性を伝えたい場合は確かにこのような言い方になるだろう。そのため、書き手に非があるわけではない。
しかし、正確を期すならばこれは必ずしもそうとは言えない。例えば東映版『Kanon』の舞ルートでは、生徒会編として久瀬との確執を数話かけて原作に沿った形で描いたが、京アニ版は大胆にカットしており、更に舞ルートのクライマックスの展開も原作よりかなり整理されオリジナルな描写になっている。これは原作のシナリオライターである麻枝准の監修によるものだが、いずれにせよ京アニ版の『Kanon』では舞と真琴を中心にオリジナルの描写がかなり入ることになったのは事実だ。また、そもそも、複数ルートが並列しているゲームを1本のストーリーにするにあたっては必然的に大きな改変を行わねばならず、そのなかで犠牲になったものが存在するのは京アニ版も東映版も共通している。
以上のように、必ずしも「東映版は原作とは違う、京アニ版は原作に忠実」とは言い切れないような細部は確かに存在している。そういった部分を明らかにすることも本企画の狙いの一つである。
本誌にはアニメファン、Keyファン、出﨑統ファンなど様々な立場の書き手15名に寄稿していただき、様々な観点から東映版Key作品の固有の魅力に迫ることができた。
当初は思い付きから始まった企画だが、東映版『Kanon』への熱いファン語りや、劇場版『AIR』『CLANNAD』への緻密な分析が集まったことで、本に魂がこもったものになった。
読者にむけて、作品に対する新たな見方を提供できるという意味では、先行する書籍や同人誌には決して負けていない。
また、イラストでも作品の魅力を表現するため、総勢14名の素晴らしい描き手に、作品にまつわるトリビュートイラスト・漫画を寄稿いただくことができた。ファンアートだけでも見応えのある本になっている。
本誌は東映版のいずれかの作品が好きな人だけでなく、京アニ版や原作のファンにも楽しんでもらえる内容を目指した。作品のファンはもちろん、これから作品を触れることを考えている人にも楽しんでもらいたい。
最後に、サークル名の「Little fragments」は『Kanon』のBGMのタイトルになぞらえて命名させていただいた。「Little fragments」は『Kanon』の主題歌「Last regrets」(麻枝准が作曲)のフレーズを用い折戸伸治が作曲したBGMだ。その「小さなかけら」の意味もあいまって、マイナーな位置づけながらも確かにKeyのゲームから派生して世に出た東映版Key三部作を形容するに相応しい言葉と思い、使わせていただいた。
ぜひ本書を楽しんでいただき、作品について興味や関心を持っていただければ幸いである。
「東映版Key三部作」の語られなさについてのコメント
私事ですが、現在いわゆる「東映版Key三部作*1」についての同人誌を制作しています。
【募集】
— highland (@highland_sh) 2020年3月8日
現在東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』の三作について同人誌を制作する計画を進めています。評論や感想、レビュー、イラストの寄稿についてご興味ある方はリプライやDMにてこのアカウントにご連絡ください。
現状語られないままになっているこれらの作品について語る場を作ろうという企画なのですが、この企画について、鍵ファンでリトバスファンの人から「アニメ版『リトルバスターズ!』の方が語られていない」とコメントがあったというのを聞きました。
確かに、『Keyの軌跡』(坂上秋成、2019年、星海社新書)においてもアニメ版『リトルバスターズ!』は(「東映版Key三部作」と同様に)存在が触れられているのみで内容については言及がなかったですし、まとまった形での考察記事を見た記憶はありません。
しかし、「東映版Key三部作」と比べるとアニメ版『リトルバスターズ!』の方が量的にも質的にも語られていると感じますし、また、両者を単純に比較することはフェアではないと考えます。
もちろん、その方のことなので、何がしかの考えをもとに発した意見には違いありません。また、直接聞いたわけではないので実際はどのような文脈での発言だったのかまでは分かりません。そのため、単純にその方の発言を批判するわけではないです。
ただ、「アニメ版『リトルバスターズ!』の語られなさ」を比較対象にして、そこからの違いとして、「東映版Key三部作の語られなさ」について考えることには意義があるかもしれないと思いました。
そこで、「アニメ版『リトルバスターズ!』の語られなさ」が「東映版Key三部作の語られなさ」とどのように異なるのかということについて、以下では考えてみることにします。
1.作品単位でバッシングされていない
まず、アニメ版『リトルバスターズ!』については批評的な言及は少ないかもしれませんが、作品に対しての表立ったバッシングはあまり見たことがありません。
それまで『AIR』『Kanon』『CLANNAD』のアニメが京都アニメーションの手により制作されていたため、『リトルバスターズ!』の制作担当がJ.C STAFFであることで多少物議を醸していた記憶がありますし、消極的な意味ではあったかもしれませんが、作品が放映されている最中にネットで炎上したりといったことはなかったのではないでしょうか。
一方で、東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』について、日本語圏のSNSや映画感想サイトで検索をかけると否定的な意見も強いです(これについては様々な要因があるかと思いますが、ここではそれについて詳しく検討はしません)。
アニメ版『リトルバスターズ!』については、一般には「J.C STAFF制作で、原作を尊重し職人的に作られたアニメ」というイメージが強いかと思います。そのため、原作ゲームのファンやアニメファンの目も冷たくないですが、一方で、批評的な言及がなされることも少ないのは確かです。
一般的に、批評家筋の人は大体いつも京アニやシャフト、元ガイナックス組の作品については語りたがるのですが、マスに対して同じくらい大きな影響力を持っているJ.C.STAFFやA-1 pictures/CloverWorksについて批評的に語ることは少ないです。
もちろん、これらのスタジオの作品が語られ得ないのはそれ相応の要因や事情があるのですが、それは少なからず、「職人的に作られている」という見方も大きく左右しているのだと思います。
京アニの作品も「徹底的に原作に忠実」と言われていますが、京アニの作品が注目を集めたのは、単に「原作に忠実」であるというのを超えて、原作のデザインや演出を鮮烈な形でアップデートして提示していたからだと思います(そういった意味で、京都アニメーションの作品を「原作に忠実」という形で言い慣わしていたのでは、取りこぼされてしまうものは大きいと思います)。
そのため、もちろんJ.C.STAFF版もきちんとした形で語られるべきだと思いますが、京アニ版を語るのと同じような形で語ることはできず、それ相応のやり方を見付けなくてはならないでしょう。
アニメ版『リトルバスターズ!』がどのように原作のシナリオをまとめているかについてここでは触れませんが、「東映版Key三部作」で脚本を務めた中村誠さんと多数の作品を共同で手がけた島田満さんがシリーズ構成を務めており、その点一つとっても語りがいのある作品かと思います*2。
2.確実な地位を得ている
上で述べた観点とも重なりますが、アニメ版『リトルバスターズ!』は「東映版Key三部作」と比べて確実な地位を得ていると思います。「確実な地位を得ている」というのは、「言説に対し抑圧的な力がない」ということでもあります。
まず、『Keyの軌跡』にアニメ版『リトルバスターズ!』の内容紹介がないことについては、個人的には「紙幅の都合」という理由で、十分に了解することができます。
というのも、仮にもう数節分のページが「Keyとアニメーション」の章に割かれていたとすれば、アニメ版の『リトルバスターズ!』『Rewrite』『planetarian』についても簡単に紹介文が載っていたかもしれないと考えられるからです。しかし「東映版Key三部作」についても同じことが言えるかというと、少し懐疑的になってしまいます。「東映版Key三部作」が得ている地位は、ごく不確実なものであるためです。
例えば、雑誌「コンプエース」の2011年7月の増刊号として『Keyステーション』(一冊全体がKeyについての特集号)というムックがあり、こちらの巻頭に掲載されている公式の年表には『Kanon(東映アニメーション版)』『劇場アニメ AIR』『劇場アニメ CLANNAD』がばっちり記載されています。即ち、作品の存在についてまでは否定していません。

しかし、各作品についての特集ページを見るとこれが怪しくなります。


こちらのムックには過去作として『Kanon』『AIR』『CLANNAD』についても特集ページがあり、それぞれの作品のゲーム版及びアニメ版についてページが割かれているのですが、載っているのは京都アニメーション版の『Kanon』『AIR』『CLANNAD』のみです。東映版についてのページはありません。
また、『Kanon』アニメ版についてのページ(画像右)には「原作発売から7年の時を経て、京都アニメーションが制作したアニメ版『Kanon』」という記載があったりするのですが、『Kanon』のアニメ化は2002年に制作された東映版『Kanon』が最初です。つまり、嘘の記載をしているわけではないのですが、Key作品の最初のアニメ化が東映版『Kanon』であったという事実を覆い隠すような記述がされています。
そしてこの「存在については触れるけど、内容については触れない」という構造はそっくり『Keyの軌跡』にも引き継がれています。こういった扱いについて「紙幅の都合」と割り切ってしまっていいのでしょうか。
客観的なスタンスから作品を見ている批評者であれば、『Kanon』『AIR』『CLANNAD』が京都アニメーションによってだけではなく東映アニメーションによってもアニメ化されているという事実は興味深いと感じるはずなのですが、それが記述に反映されなかったのは残念であるなと思います*3。
『Keyの軌跡』について、私がとりわけ困惑させられるのは『Kanon』のアニメについての記述であり、京アニ版『Kanon』の構成を称賛する記述をしていながら、同じ問題に取り組んで一定の成功を収めた東映版『Kanon』のシリーズ構成については一切記述がないことです。著者はただ、それらの記述について「東映版『Kanon』の場合はこうしていたが、京アニ版は~」とただ一言ずつ加えるだけで良かったのですから。
また、上記の事柄以外にも、「Key作品のアニメ一挙放送」のような企画でも東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』についてはラインナップにないことがほとんどですし、Key20周年特設サイトの関係者コメント欄に東映版の関係者が不在であったりするのを見ると、やはり地位の不確実性を感じざるを得ないところがあります*4。
ただ、これについては、Keyファン層や原作ファン層からの外圧というのもあるでしょうし、おそらく権利的な要因もあるのかなと思っています。
3.比較対象の不在
これについては非常にシンプルです。
『Kanon』『AIR』『CLANNAD』のアニメは東映アニメーションだけでなく京都アニメーションによっても制作されるという極めてイレギュラーな事態が発生し、両者は必然的に比べられることになりました。
そのため、東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』について、褒めるにしても貶すにしてもそれは「京アニ版との比較」によって語ることになってしまい、必然的に「アダプテーションのあり方」に関する議論にならざるを得ない状況にあります。
そしてその点で、諸々の要因によって「東映版Key三部作」は「京アニ版Key三部作」について分が悪く、それが現在に至るまでの地位に繋がっているということです。
当然ながらアニメ版『リトルバスターズ!』については一作しか作られていないため、ずっと素直な形で評価を行うことができます。
J.C.STAFF版『リトルバスターズ!』の後に京アニ版『リトルバスターズ!』 が作られたり、J.C.STAFF版の『リトルバスターズ!』が『劇場版 リトルバスターズ!』として公開され、それと並行して3クール分のアニメがTVシリーズとして放映されることはありませんでした(「東映版Key三部作」に対して起こったのはまさにそういうことなのですが)。
また、以上に述べた三点の理由以外にも、単純に、言説の量的な意味でもアニメ版『リトルバスターズ!』は「東映版Key三部作」よりも語られていると思います。
例えばアニメ版『リトルバスターズ!』の感想をネットで検索すると、まとまった形のブログ記事に多数辿り着けますが、『劇場版 CLANNAD』について検索すると辿り着ける記事の多くは公開当時に書かれたもので、それ以降はほとんど(まとまった形での)記事が書かれていないことが分かります。
結論としては、現状アニメ版『リトルバスターズ!』についてもあまり語られていないかもしれませんが、「東映版Key三部作」を取り巻く状況と比べると見通しは明るいのではないでしょうか。アニメ版『リトルバスターズ!』についての論が書かれることを期待したいところです*5。
*1:東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』をまとめての呼称ですが、「東映版Key三部作」という呼称は公式なものではなく、あくまで便宜上の言い回しです。
*2:個人的には、樋上いたる先生とNa-Ga先生のキャラクター原案をアニメーションにするにあたってそれらを上手く折衷できる絵柄の飯塚晴子さんをキャラクターデザインに抜擢したのは慧眼であったと思っています。
*3:『Keyの軌跡』についてはKeyの公式が監修しており、多かれ少なかれKeyやVisualArt'sのスタンスが反映されていると思うため、単純に著者の坂上氏を批判するわけではありません。坂上氏の現在の立場も、完全に独立した批評者というよりは、どちらかというとKeyの広報に寄ったものであると認識しています(これについても単純に良い悪いというわけではありません)。
*4:他方で、「東映版Key三部作」は海外サイトでも配信がされたほか、国内においても、Netflixで『劇場 CLANNAD』がBD画質で配信されたりしています(2020年5月24日現在)。また、『オールアバウト ビジュアルアーツ~VA20年のキセキ~』(2013年、ホビージャパン)でも東映版『Kanon』『劇場版 AIR』『劇場版 CLANNAD』はサムネイル付きで短い紹介文が載っています。加えて、Keyの公式サイトの年表でもこれら三作品は記載されており、「存在を認められている」ことは確かで、「なかったこと」にはされていません。
一部の「東映版Key三部作」のファンの中には、自分たちの好きな作品のことを「黒歴史」と称する人もいますが、本当に「黒歴史」のように扱われているのであれば、こういったこともされていないはずです。必要以上に自虐的になる必要はありません。
アニメOPに見る画面の立体感とテロップの表現
今回は純粋に視覚的な事柄について書きます。季節外れな話題になってしまいますが、ご容赦ください。
最近アニメのOPテロップについて色々と調べているのですが、その中で思い当たったのが『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』(2013)のOP。古いとかは言わないでください。


一応OP映像について紹介すると、疾走感あるメタルなアレンジのオープニング曲に合わせ、もこっちこと黒木智子の殺伐とした心象風景を描いたクールなOPで、国内外で多くの反響を呼びました。TVアニメのOPなのに主人公一人しか画面に登場しないのもストイックです。
本記事で取り上げたいのは、このOPのうち上に掲載した2カットで、もこっちの歩き姿をそれぞれ前と後ろから捉えたものになっています(2カット目は上下反転)。
このOPの絵コンテ・演出を手掛けたのは監督でもある大沼心さんで、キャラクターの歩き姿を望遠で捉え、コントラストの利いた絵で横に伸びる影を映すといった表現はかつて大沼さんの師匠筋であった新房昭之さんも自身の監督作でよく使っていた手法ですが、
左から『The Soul Taker ~魂狩~』OP、『銀河お嬢様伝説ユナ〜深闇のフェアリィ〜』OP
その望遠の絵に鎖を大胆に絡ませて、視野の間近まで鎖を伸ばすことで、手前は広角で画面奥側は望遠の絵になり、誇張されて歪んだパース感覚により幻惑的な効果を生じさせています。
それにしても、これ凄まじい立体感ですよね。
この立体感(画面から飛び出してくる感じ)を生んでいるのは画面上下の黒い帯と、色付きの影の線だと思います。黒い帯が映像のフレームを狭める枠のように見えていて、それを乗り越えて上下左右に鎖が伸びていることで、フレームをまたいで飛び出してくるように見えています。
また、色付きの影が付いていることで画面内でキャラクターがどれだけ遠くにいるかが分かり、画面手前と奥側とで異なるレイヤーになっていることが直感的に分かるようになっています。
立体感を醸し出しているもう一つのポイントは、画面内でのテロップの位置です。このテロップはあたかも画面内の物理的空間において浮かんでいるような見え方をしています。


それぞれのカットについて、テロップが存在するように見える位置を赤と黄の丸で示してみました。同じ色の矢印で、鎖の伸びている方向も示しています。
上の方のカットでは鎖がテロップの位置の上側、下側、奥側に伸びていることで、鎖が作る三角形の中にテロップが綺麗に収まって見えます。
下の方のカットはそれより複雑ですが、もこっちの足元(画面上側)から伸びる鎖は下側へ、もこっちの上半身(画面中央)から伸びる鎖は水平に近い角度で画面のこちら側に伸びていることで、その中間のスペースにテロップが漂っているように見えます。
どちらのカットにおいても、鎖が伸びる位置と方向によって「高低差」と「奥行き」のあるスペースができており、そこにテロップを当てはめることで、文字があたかもその物理的空間において浮かんでいるような見え方をしています。
もちろん、鎖の揺れる動きや振れ幅と、テロップのモーションが完全に連動していることも、テロップが物理的に存在しているような印象を作り出しています。
この「テロップの文字があたかも画面内の物理的空間において存在しているような見え方」のことを、以下では「テロップの物理的実在性」と表すことにしましょう。
『わたモテ』OPの当該2カットは「鎖と枠線による立体感の表現」に「テロップの物理的実在性」を絡めることで、立体感の効果を底上げしていると考えられそうです。
***
さて、大沼心さんは他にも、これと同じように創意工夫を凝らした立体感の表現をやっていて、『六畳間の侵略者!?』(2014)のOPがそれに当たります。古いとかは言わないでください。
このOPについては放映当時、当ブログで記事にしていました。
そしてこちらは上掲の『六畳間』の記事でも引用した立体感のテクニックについての記事です。
当該記事で添付されているgif画像の内一つだけ引用すると、

犬が画面のこちら側にZ軸方向で迫って来るのに合わせて、犬があたかもその線をまたいでいるかに見えるように左右に白線を入れることで、3Dっぽい立体感が生み出されています。
もしこれを大きめのスクリーンでご覧になっていたら、片目をつぶってもらって、人差し指を二本前に出して白線を覆ってこのgifを見てみると、この錯覚は生じなくなっているのが分かるかと思います。
このような錯覚が生じるのは、恐らく白い線が物理的な何かのように見えるのもありますが、「白い線があるレイヤー」イコール「画面の枠」のように認識するからでしょう。
つまり、白線をまたぐ運動が入ることで、「画面の枠」となっているレイヤーを飛び越えて画面から飛び出してくるような感覚を生んでいるのではないでしょうか。
(このブログの背景が今は白一色に設定されているため、画面内の白線とブログページの背景とが連続したものに見えることで、立体感がより増して感じられるようになっています。)
この内容を踏まえて『六畳間』OPを見てみて下さい。以下が当該シーンのgif画像になっています。

(最初と最後が繋がって見えるため無限に回り続けているgifになりました。)
主人公からのPOVでカードゲームをしているという趣向で、オープニングではこの調子でカットを割らずに3周もカメラが回るのですが、このgifは1周目の部分です。上記事で紹介されている表現が見事に活用されているのが分かります。
記事内容と直接は関係ないですが、ヒロイン4人の名前を紹介すると早苗→ティア→キリハ→ゆりか、の順番に回っていきます(最初の紫髪のキャラが早苗です)。
ここでは立体感の表現について詳しく見たいので、まずキャラクターと白線、テロップのレイヤー関係を確認しておきましょう。

キリハの場合、後ろに一対の埴輪がいるので分かりやすいかと思います。
後ろから埴輪→キリハの上半身→白線→キリハの腕→テロップの順にレイヤーが重なっているのが確認できます(主人公の持つカードも手前に見えますが、これとテロップとが同じレイヤーかどうかは少し曖昧です)。
注目すべきポイントとしては、ここでキャラクターの動きは白線をまたいで越えてくることはあっても、テロップより前にキャラクターの身体が出てくることはありません。従って、ここでのテロップは常に画面の一番上のレイヤーに位置していると言えます。
ここで、先ほどの1周目のgif画像を、テロップと白線だけに注目して見てみてください。カメラが回転するときに、テロップが白線に貼り付いて動いているように見えるかと思います。
しかし実際には、この二本の白線とテロップは、カメラの回転に合わせて動いたりはせずその位置はあくまで画面内に固定されています。
なので、カメラが回転するのに合わせてこの二つは一緒に動いているように見えるのですが、それは錯覚で、実際にはこの二つは定位置にあって、あくまで背景が動いているからそう見えているだけという訳です。
ここでのテロップは白線に貼り付いて動いているように見えますが、このことが更に面白い効果を生んでいます。先ほども述べた通り、キャラクターが白線をまたいでこちらに手を伸ばしてきたときに、その身体の一部がテロップを越えてくることはないため、実際には、テロップと白線との間には(画面内の物理的空間において)かなりの距離があるということが分かるのではないでしょうか。
つまり、このカットにおけるテロップと白線とは「貼り付いて同じレイヤーにあるように見える」と同時に「実際には大きく離れているように見える」という奇妙な関係になっています。見れば見るほど不思議な感覚になってくるカットです。
これまでは当該カットの1周目の回転について見てきましたが、2周目になるとテロップと白線との関係は更に面白いことになっています。

こちらが2周目の回転のgif画像になっているのですが、後半の二人(キリハとゆりか)のパートで、テロップの置かれている位置が1周目のときと少し違っていることが分かるでしょうか。


静止画で見るとこのような感じになっています。キャラクター、白線、テロップのレイヤー関係は1周目のときと同一ですが、今回は「左側にあるテロップは白線の前」で「右側にあるテロップは白線の後ろ」にあるように見えてこないでしょうか?
これはちょっと不思議な現象が起きています。

先程の1周目の絵でのテロップの位置を確認すると、上画像でいうテロップ1もテロップ2も、その文字が白線に重なるように置かれていることが分かります。

2周目の絵でも、テロップの位置は二つとも同じですが、こちらはテロップ1での「美術監督」と「森尾麻紀」との間にある「 」のスペースに白線が通るようにしており、それによって、上画像のようにテロップ1だけが後ろに入り込んでいるように見えてきます。
これは恐らく、テロップの文字はワード2つが離れていても1セットとして認識されるために、塊になって後ろに入り込んで見えるのだと思います。「テロップの物理的実在性」がここにおいても生じていることが分かります。
興味深いのは、このカットでは別にテロップを後ろの方のレイヤーに組み込むようなややこしい処理は全くしていないということです。テロップはあくまで映像の上からそのまま付けられていて、しかも画面内の定位置にあり動きません。
にもかかわらず、テロップの位置を操作するだけで後ろ側のレイヤーに入りんでいるように見えて、しかも白線とテロップとがその位置関係を保ったまま動いている……という錯覚が生じています。こういったシンプルな工夫によって立体感が醸成されているのが面白いです。
ちなみに、このテロップ1と2の位置を変えると下の早苗の絵のようになります(こちらは3周目の回転に出て来る絵です)。

主人公が伸ばしている手がないために、2周目の絵より白線とテロップの関係が分かりやすいかと思います。こちらでも左上のテロップが白線の手前で、右下のテロップが白線の奥側にあるように見えています。
更に言えば、この回転のカットは全体を通して、キャラクターの背景にある部屋がアオリのアングルで捉えた絵になっているために、カメラが斜め下側から↗方向を向いて撮っているように見えます。
そのため、二本の白線はデフォルトで斜め上に向けてかかっている(画面の手前側に傾斜している)ように見えるのですが、上画像のような絵だと、テロップの置かれている位置に合わせて白線の伸びる方向が変わっているように見えます。
「左側の白線は画面奥側」に傾いて伸びていて「右側の白線は画面手前側」に傾いて伸びているように見えてこないでしょうか?
こういう風に検討していくと、色々な見え方をする画面になっていることが分かり興味が尽きません。
まとめると、『六畳間』のOPは錯覚を活用することでテロップや白線、キャラクターの身体といったレイヤー間の関係を攪乱し、立体感/奥行きを生じさせることに成功していると言えるでしょう。そして「テロップの物理的実在性」もそうした効果を出すのに一役買っていることになります。
***
ここで、ともに大沼さんの手掛けた『わたモテ』と『六畳間』OPの共通点を、「テロップの物理的実在性」の観点から考えてみたい。
今でこそ「テロップ一体型」スタイルのOP(e.g.石浜真史)は多くなっていますが、一般的に、OPやEDでのテロップは通例としてビデオ編集(V編)時に完成映像の上から付けられるので、そもそも「キャラクターのいるレイヤーの上側(画面手前側)にある」というのが標準の仕様です。概ね視聴者の人もそういう感覚で見ていて、通常、映像それ自体とテロップとは分けて捉えているでしょう。
なので、普通、テロップを用いて立体感を出したいならば多くの場合はテロップのあるレイヤーをキャラクターのいるレイヤーと重ねたり、テロップをキャラクターの手前ではなく奥側に配置したりといったことがなされていると思います。
例えば、こうした手法で卓越したテクニックを見せている演出家には大畑清隆さんがいます。彼が手掛けた『WORKING!!』シリーズのOPではテロップの描かれたボードがキャラクターと同じ物理空間に存在し、テロップとキャラクターとの絡みがあるし、また、テロップがキャラクターの奥側にあることも多く重層的な表現になっています。




上2つがが1期OP、下2つが2期OPのものです。
また、この立体感はレイヤーの位置変更だけでなく影付けによって生み出されている面も大きいです。キャラクターや物体の影がシルエットの形になっていて、しかも実像とは大きくズレた位置にあるため背景から浮き上がって見えます。また、影の幅の大きさがオブジェクトの種類によって異なるため、例えば左上のカットでは「『WORKING』と書かれたテープ」「テロップのボード」「キャラクター」とが別のレイヤーにある(背景からの距離が異なる)ことが一目で分かるようになっています。
『WORKING!!』シリーズを始め大畑さんの手掛けたOPは他にも面白い表現が目白押しですが、本筋から外れるのでここでは大沼さんのOPに話を戻します。
これまで見たように『わたモテ』『六畳間』OPは、どちらもテロップが画面内のオブジェクトと同じレイヤーにあったり、奥側に入り込んでいたりする「ように見える」ことが、画面の立体感を出すことに繋がっていました。
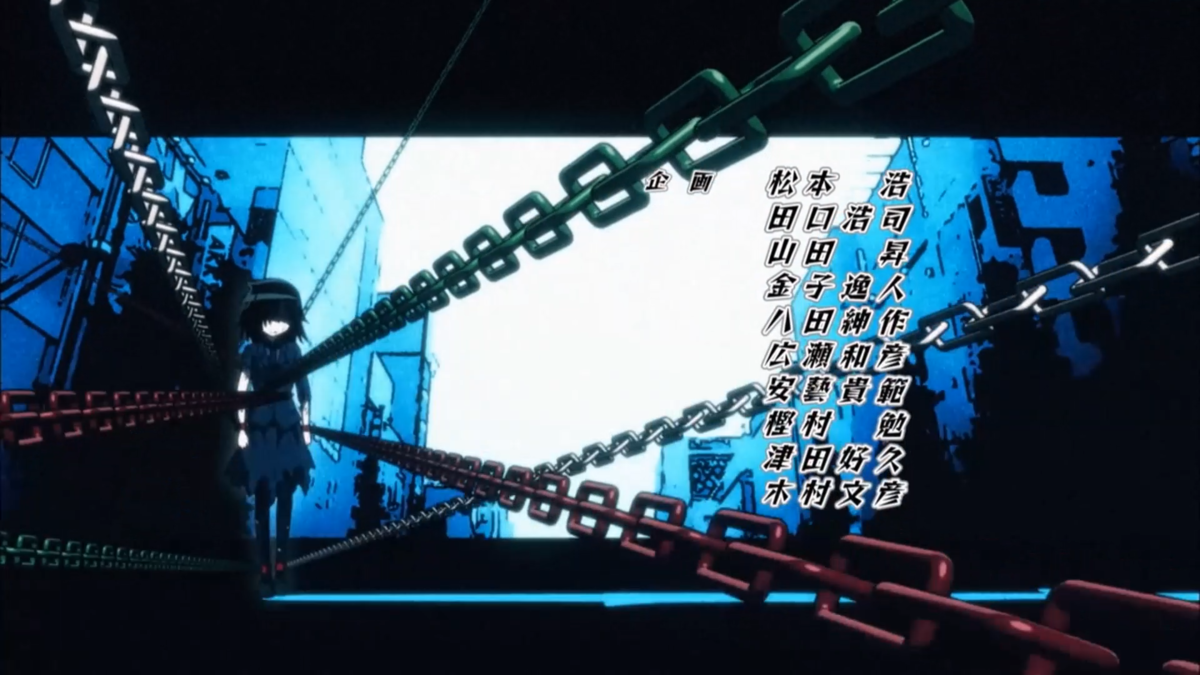

しかし実際にはそのどちらにおいても、大畑さんがやっていたような「テロップのレイヤーをキャラクターの後ろ側に入れる」といった処理はやっていません。
見てみると分かるようにこれらOPにおいて「画面内にある他のオブジェクトがテロップの文字より上に来る」「他の絵がテロップに被さる」という絵は1フレームも入っていません。なのでテロップはあくまで「完成映像の上から付けられた」ようなスタイルを取っているのですが、にも関わらず、錯覚を活用することで「テロップの物理的実在性」が醸し出されており、それが立体感にも繋がっています。
大畑さんのような「テロップ一体型」スタイルではないのに、『わたモテ』『六畳間』OPは「テロップ一体型」と同じような効果を生んでいて、それが非常に面白いなと思ったので、今回記事を書かせていただきました。
***
また、アニメのオープニングという枠から外れますが、これまでの例において取り上げたようなテロップや枠線の使い方について、最近自分が見つけた類例としては茜新社刊の成年向け漫画雑誌「COMIC アオハ」(2019年に創刊)の表紙があります。
(はてなでは成年向けコンテンツへの扇情的な言及はNGであり、ここでは表紙デザインの話だけをすることを最初に述べさせていただきます。)


こちらが季刊誌の春号と夏号の表紙になっています。イラストレーション担当は加茂さんという方。
下の方に、それぞれピンクと水色の帯のようなものがあって、これが不思議な効果を生んでいますね。
一般的にこうした帯というのは紙書籍のカバーの上から被せられるという前提知識があるわけですが、この帯は表紙のデザインにあらかじめ組み込まれています(実際この雑誌の紙書籍版でもそうなっています)。
そして、通常であれば帯がキャラクターと被さる部分で色も重なるはずですが、この表紙では帯下の部分のうちキャラクターの身体だけがそのままの状態で露出しており、帯の上側(手前側)にキャラクターがいるように見えています。
そして帯の上側にキャラクターがいるために、単に立体感が出ているというのに留まらず、キャラクターが表紙から浮き出ているように見えることで「実在感」をも強烈に感じさせるデザインになっています。
また、帯より上のレイヤーにあるのは女の子のキャラクターだけではありません。春号の表紙ではキャラクターの更に手前に桜の花びらが舞っており(この花びらの大きさと位置とボケ具合が絶妙であることに注目して欲しいです)、花びらがキャラクターのかなり手前に見えることから、表紙にあたかも3Dのような立体感が付与されています。
そしてここにおいても、帯に付けられたキャプション(宣伝コピーやレーティング、価格等のマーク)の文字が、アニメOPでのテロップと同様に効果的なデザイン要素となっています。
春号と夏号の表紙ともに、キャラクターの身体を隔てて左側と右側にキャプションが付いていますが、上の画像を見ていただくと「左側のキャプションはキャラクターの手前」にあって「右側のキャプションはキャラクターの奥」にあるように見えてこないでしょうか?

春号・夏号それぞれについて、キャプションはあくまで表紙の上に置かれており、一番上のレイヤーにあります。にもかかわらず、キャプションの1と2とでは互いに離れたレイヤーにあるように見えて来てきます。
考えられる理由としては、
- キャプション2は平面的で輪郭線がない文字であるため帯に貼り付いて見える(従ってキャラクターより奥側にあるように見える)。
- キャプション1の背景は空間が詰まっておりキャプション2の背景では空間が開けている。春号では「キャラクターのお尻」と「奥行きのある道」とで差異があり、夏号では「階段の上の段」と「下の段」とで傾斜がある。
の二つでしょうか。
特に夏号の方は、春号と違ってキャラクターに被さっている文字が何もないのにレイヤーが違って見えているのがとても不思議です。これは恐らくキャプション1のある部分が影になっており暗く、キャプション2の部分が明るくなっているために違いが強調されているのもあると思います。
そしてこれは、「キャプションはあくまで表紙の上に置かれている」にもかかわらず「左右のキャプションでレイヤーが手前と奥側の異なるレイヤーにあるように見える」という点が、先ほどの『六畳間』OPにおけるテロップの技法と共通しているのが分かるかと思います。

「COMICアオハ」の表紙は帯を、『六畳間』OPは白線を文字と絡めて利用しており、両者は図らずも似通ったものになっていますね。
異なるアイディアからアプローチをかけたであろう両者のデザインが、立体感を表現するために同じような方法を取っていることの興味深さを感じていただければと思います。
画像はここでは貼らないですが、「COMICアオハ」はその後秋号と冬号が出ていて、それぞれで新しいデザインの表紙になっています。個人的な意見としては、秋号は正直ちょっと攻め過ぎなレベルの前衛性になっていて、逆に冬号は大人しいデザインになっているという印象なのですが、どうでしょうか。気になる人は調べてみてください。
まとめ
結論といったほどのものは特にないですが、画面の立体感を出すための技法には様々なものがあり、ときにテロップの表現を絡めることでその立体感を底上げできるということを示せたと思います。
人間の錯覚を利用した表現って面白い……!と感じていただければ幸いです。
アニメOPと画面の立体感ということについては、松根マサトさんを始めとするOPディレクターによるモーショングラフィックスを活用した表現についても触れたい所ですが、それについてはまた別の機会にしようと思います。
おまけ
ちなみに、『WORKING!!!』3期のDVD・BDパッケージソフトのカバー(足立慎吾さんによる版権イラスト)でも「WORKING」テープを活用した立体表現が見られます。


このテープはもともと原作漫画の表紙にあったデザインで、それを基にしてアニメ版のOPも作られているのですが、このパッケージイラストは大畑さんのOP演出のスタイルを取り込むことで、立体感を更にグレードアップさせています。原作漫画のスタイルをもとに表現を発展させていった好例だと言えるでしょう。

私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! (16) (ガンガンコミックスONLINE)
- 作者:谷川 ニコ
- 出版社/メーカー: スクウェア・エニックス
- 発売日: 2019/11/12
- メディア: コミック
劇場OVA『フラグタイム』(2019)感想

同じく劇場OVAとして公開された『あさがおと加瀬さん』に続き佐藤卓哉さんが監督を手掛け、『加瀬さん』は新書館の百合レーベルより刊行された漫画が原作でしたが、今回は純粋な百合レーベルではない、秋田書店の少年誌レーベルより刊行された漫画が原作の作品となりました。
制作会社が違うこともあり、作画に関わるスタッフは前作と大きく異なるのですが、音楽担当のrionosさんをはじめ色彩設計、撮影、編集といったセクションの方は共通しており、こうしたポスプロ関連の陣営が共通していることで前作と共通したテイストを残すフィルムになっています。
ファーストショットは黒背景に時計の刻むチクタクという音から始まり、砂地に映し出される文字、そこから公園の砂場、海岸の浜辺と映し出され、それら両者がともに「砂時計」のモチーフで繋がっていることが示されたところで、舞台は主人公のいる学園へと移っていきます。
このシークエンスからも分かるように本作においては砂場や海岸、砂時計、更には鳥や電柱といったイメージがしばしばインサートされ、学園を舞台にした二人のドラマを引き立たせています。
砂場は幼稚園や幼少期のイメージと結び付いており、これはトラウマや本心を幼少期の自分として表現する演出でしょう(『エヴァ』とか『アイマス』とかで見られたような)。
海岸のモチーフはラストで、映画版のキービジュアルにあるような、二人が屈託なく逢瀬を交わせる場に繋がっていきます。

砂時計は砂場と海岸の両者を結びつける媒介となるもので、冒頭のシークエンスにおいても時間が停止すると同時に遊ぶ子供たちや、浜辺に寄せる波が止まるイメージが描かれています。
随所に挿入される、砂場に映し出される文字は心象風景であると言えますが、この演出が発展していった真骨頂と言えるのは、森谷さんが村上さんのベッドの引き出しを開けた時に、砂場の土が最初に画面一杯に映るシーンで、これは鮮烈なイメージで思わずどきっとさせられた所です。
村上さんの単語帳は実際に原作でもかなり闇を感じさせる描写で、「ベッドの下は見ないでね」という言わば誘い水となる台詞を受けた森谷さんが、村上さんが奥に秘めた内面を直視することを選択した局面で出て来るものです。それだけの強い表現として描く必要があり、不気味さを演出する効果的な見せ方になっていました。
以上でも述べたように『フラグタイム』はイメージ先行型のフィルムで、見方によっては前衛映画と言っても良い作りだったので少し驚かされました。そしてこれはもちろん「静止して隔絶された空間を通じコミュニケーション/ディスコミュニケーションを描く」という本作の題材と結び付いたものなのですが、ことによると本作の制作環境と結び付いた作りであるかもしれません。
前作の『加瀬さん』の方は、佐藤監督が長年パートナーとして組んでいる坂井久太さんが総作画監督を務めていることもあり、イメージの飛躍は抑え目な代わりに、一つ一つの表現(レイアウトや作画)についてじっくり愛着を持って作られている感じが出ています。
逆にティアスタジオで制作された『フラグタイム』は、艶のある作画のキャラクターをあまり動かさない方向性で、音響と美術で見せる静的な趣向(オーディオドラマ的と言うべきか)になっており、アニメートそれ自体ではなくイメージを主体に構成していく作りになっています。そしてそのことによって、逆説的に、佐藤監督の作家性を『加瀬さん』よりも強く感じさせるものになっていました。
本作の評価についてはざっくり以上のようにまとめられそうなのですが、他方で、さと先生の『フラグタイム』の原作を既読の状態で鑑賞した身としては、微妙な気持ちになったのは事実です。
以下では映画の感想について話を移し、本作についての個人的な考えを述べてみたいです。なお、劇場で一回見ただけの感想なので記憶違いがありましたら訂正します。
まず指摘しておきたいのは、映画版『フラグタイム』は、基本的には漫画版と同じ流れのストーリーなのだけれど、台詞であったり演出だったりの細部を変えることで、違う内容とメッセージになっているということです。つまり、実際のところ、直ぐ様それと見て取れる大きな改変はないのだけれど、細部を変えているので違った印象を受ける作品になっています。
映像化の際になされた改変はいくつかありますが、自分が決定的だと思ったのは、
- 主人公/森谷さんが最初に村上さんのスカートをめくるまでのシーンで、モノローグをなくしている。
- 最後に主人公と村上さんが廊下で言い合いの喧嘩をするシーンで、周囲を取り囲む生徒たちがいなくなっている。
の二点です。この二点があることによって、印象も意味合いもだいぶ違ったものになっていると思います。
モノローグについて
まず1.についてですが、モノローグ全般について述べると、映画を見た方は主人公のモノローグがそこそこ多いためあまりそう感じなかったかもしれませんが、原作のモノローグはこれでも割と削っていて、主人公の赤裸々な内省や一人語りはそれほど露骨ではなく、自意識過剰な感じがあまりなくなっています。
漫画の方は、ほぼ一貫して主人公の内面に視点が入り込んでいて、主人公の本音や欲望を滲ませた明け透けな独白に自己を重ねる形で読者は読むし、村上さんが主人公に対してする挑発には「お前はこういうことがしたいんだろ?」と読者も同時に言われているような感じもして来ています。
映画版ではそういう露悪的なニュアンスがなくて、そのため、奥手でコミュ障な主人公が村上さんの言動に翻弄されていくという図式は漫画版と変わりないですが、内部に視点が入り込むのではなく「一対一の対話」で、外から眺めている感覚に近いため、不器用ながら相手に手を伸ばしていこうとする意味合いが最初から強く出ていました。
つまり、モノローグを削ったことで主人公/森谷さんの自意識は原作と比べ希薄なものになっています。
原作と同じ流れながら印象を変えているシーンの例として、例えば原作での第1巻80頁前後に当たる、保健室にて保険医さんの目前で時間を止めて主人公が村上さんにキスをするシーンがあります。

映画版ではこのシーンの流れは、最初に村上さんが主人公に挑発するような調子でけしかけることで、主人公が時間を止めてキスする流れだったと思うのですが、原作では主人公が衝動的に時間を止める選択をして、その後願望を正直に吐露する流れになっています。

このシーンでの「時間を止めてキスをする」という行動や、起こるイベントの内容、「自分がしたいことを主体的に表明し相手にぶつける」という結論それ自体は原作でも映画版でも同じです。
しかし、原作では(作中での表現を借りれば)主人公の「変態」「童貞」っぽさを感じさせるシーンが、映画版だと村上さんの方が小悪魔的な感じで主人公をけしかけることで、主人公のぎこちなさという要素は消え、むしろ「村上さんに翻弄される」という主人公の立ち位置が前景化しています。原作にあった、主人公の欲望/願望の要素が削られることで、異なる印象を与えるシーンになっていると言えます。
こうした、「自意識を削ぐ」「(欲望を除き)清潔化する」アレンジについては他シーンでも見られ、その最たるものは、1.に挙げた「主人公/森谷さんが最初に村上さんのスカートをめくるまでのシーン」でしょう。村上さんと森谷さんの物語の起点となるこのシーンにおいて、主人公がその背景となる心情や生い立ちについて述べるモノローグは大胆にカットされており、主人公の動機については間接的に仄めかされるに留まっています。
本来であればいきなりスカートをめくるという行動は唐突であり、その後ろ暗い気持ちが明かされることで初めて了解されるような事態と言えますが、それを示すモノローグがあえて削られていることで、この行為はあくまで「二人が関係を取り結ぶきっかけ」としてのみ前景化することになっています。ここにおいても「自意識の希薄化」及び「対話の表現への移行」が顕著に見られます。
両者の違いについて、
・【原作】:主人公の内面に入り込んで村上さんに迫っていく構図
・【映画版】:一対一の交流を見ている感じ
とここではまとめておきましょう。
そしてこれは、一概に原作の要素を損なうアレンジであるという訳ではもちろんありません。むしろモノローグを最低限必要な量にまで削り、非言語的なものにしたことで映像としてより洗練されたものになっているとも言えます。
注目すべき点としては、このアレンジは、映像化に伴うモノローグの省略を機に起こったものであるかもしれないということです。前提として、時間芸術である映像では漫画のように多くのモノローグを乗せることが出来ず、また、多くのモノローグをナレーションで読み上げることは映像としての情緒を損ないます。
主人公のモノローグを削るためには、主人公がもっぱらモノローグを発することで説話を進めていくという原作漫画のスタイルからある程度脱する必要があり、そのため「一対一の対話」が際立つようなアレンジになったのではないでしょうか。
そうすると、両者の相違はメディアの違いによる変奏だと考えられて面白いです。
クライマックスシーンについて
2.については、作品のテイストというよりはそのメッセージの部分において影響を与えている変更点です。
森谷さんと村上さんが廊下で言い合いの喧嘩をするシーンで、原作では周囲を取り囲む生徒たちがいて衆人環視のもとでこの対話はなされるのですが、映画版では二人以外の誰の姿も見えない状態で、二人は本音でぶつかり合います。
原作でも映画でも、このシーンが作劇全体においても重要な意味を持つのは、それまでの物語では一貫して森谷さんが語り部として話が展開しますが、ここで初めて他者である村上さんのモノローグが入ってくることによります。それまでは主人公の推測を通してしか表されてこなかった村上さんの心情が直接入って来ることで、相手との本音での関わり合いが生まれるのと同時に、「一人の話」から「二人の話」へと作品の持つ意味合いが変わって来ます。
しかし、このシーンの描写は映画と原作とで異なったものになっています。
映画だと自分と相手だけの世界に入り(雑味のない状態で)、これまで互いに抱いていた感情に答えを出すシーンになっていますが、これは原作だと、二人の会話に被さる形で周囲を取り囲む生徒の台詞が途中から入ってきて、それを切っ掛けとして村上さんのモノローグもまた入ってくるという感じになっています。重要な点としては、村上さんが森谷さんに対して抱いている自身の気持ちに気付くきっかけを、普段村上さんに接している(森谷さん以外の)他の生徒が引き出しているということです。
そしてそのことによって、そこで彼女たち二人の関係から、ほかの皆んなを巻き込んだ関わり合いにまで話が膨らんでいく感じが生まれています。
つまり、映画だと主人公のモノローグ→村上さんのモノローグと展開することで「一人の話」から「二人の話」へと変わっていくのですが、これは原作だと「一人の話」から「二人の話」に広がるのと同時に、それを見守っている「みんなとの関係」にまで膨らんでいっています。そしてそのことによって、「みんなを前にして自らの本音を率直に出す」という性質が付与されています。
まとめると、話の水準の推移は以下のようになっていると言えるでしょう。
・【原作】:「一人の話」→「二人の話」→「みんなとの関係」
・【映画版】:「一人の話」→「二人の話」
実際、原作ではこのシーンにおいて二人の気持ちは他の人たちにも知られることになり、彼女たちのその後の境遇にも少なからず影響を与えていることが分かります。

原作ラストの上ページのシーンは映画版でもあり、モノローグの内容も多くが残っていますが、映画版だと「みんなとの関係」にまで波及は起こってないため、二人を取り巻く環境の変化はあくまで限定的です。クライマックスでの二人の言い合いが、「みんなを前にして心情を吐露する」というシーンではなくなったことで、映画版では森谷さんと村上さんの(同性愛の)カミングアウトもなかったことになっています。恐らくは「なかったことにした」というよりは、描かなくていいものとして「省略された」という方に近いのだと思いますが、いずれにせよ異なる質の結末になっていることは確かです。
映画版の作り手(ここでは仮に監督だとします*1)が、この二人の最終的な関係をどのようなものとして提示したかったのかについては、ラストシーンの描写に如実に現れています。
原作でもアニメでも、ラストシーンは最後、校内で別々のグループにいる二人が目配せするシーンで、この時に他の生徒も映っています。そうして映画版でのオリジナルの描写として、映画のラストに持ってくる絵が、キービジュアルにあった「浜辺で二人が歩いているイメージ」のショットになっています。ラストカットに浜辺のイメージが出た後、二人が足跡だけ残して消えるという描写です。
この演出は、二人の「恋愛関係がバレてしまっている」という描写の代わりに入れられたものだと思われますが、映画版の監督は、百合的な関係をどこか「秘匿されるようなもの」として提示してきている印象を私は受けます。映画版では、二人の関係性についてはあくまで「二人の間だけに通じるもの」として結論付けられているからです。
森谷さんの能力的に秘匿のイメージで映画をまとめたかったのかな、という風にも思いますが、ただ、森谷さんの能力が消えて行くことで、周囲の人たちとの関係にも変化があるというのがストーリーの本懐なので、映画版は原作と比べてどこか物足りない印象も受けます。
監督の意図としては、「みんなと通じ合えなくて上手く行かなくても、好きで分かり合える人が一人いればいい」という映画版のテーマに着地させるために、雑味となるような要素を削ぎ落としたのでしょう。あるいは百合作品として純度を高めたいということによるのかもしれません。
ただ、本音でのコミュニケーションから逃げていた主人公が、プライベートな関係や、人前で隠しておきたいことも含め丸裸にされることで吹っ切れるというこのラストシーンは原作漫画全体を通じても大きなカタルシスを生む部分であり、映画版ではそれをあくまで二人きりの対話のシーンにしたことで、そのシーンが作品に影響を及ぼす範囲は限定されてしまっています。
原作と映画版のラストにおける二人の関係は、それぞれ以下のようになっていると言えるでしょう。
・【原作】:二人の関係は特別だけれどオープンなものになる。
・【映画版】:二人の関係は特別なものであり他者からは秘匿されている。
最後に
1.及び2.の変更点を見てみることで、原作から映画版へ翻案される際に方向性の転換が起こっているということを見てきました。
個人的な感想としては、映画版への翻案を通じ原作の価値を損なうようなことはしていなかったと思うのですが、監督の美意識で作品全体を覆っていくといった面は感じられ、自分が良さを見出していた部分は削られていたような感じも受けたのは事実です。もっと毒っ気のある脚色が見たかった身としては、好みド直球とまでは行かない感じでした。
実のところ、自分は原作を元々読んでいて、アニメ化されるという報を見た時「岡田麿里脚本で映像化されるのを見たかったな」と思ったのです。
岡田麿里脚本イコール「あけすけな台詞」「露悪的な展開」「共感性羞恥を思いきり刺激されるシーン」「叫びながら互いの感情を赤裸々に吐露するクライマックス」なイメージを持ってしまうのは流石に安易ですが、実際に漫画を読んでいて岡田麿里作品のテイストを感じたのは事実ですし、岡田さんがもし脚本をされるとしたら、上で述べたような点について拾った脚色をしてくれるかもと思ったからです。ご本人も百合作品の仕事で実績の多い人ですし、岡田麿里さんが脚本書いたバージョンも見たかった…!と思いました。
ただ、このような感慨を抱かせてくれるほどに演出と作画が良かったとも言えるので、いずれにせよ視聴推奨な作品ではあります。映像ソフト化されれば良いのですが。
*1:もちろん実際にはプロデューサーや原作サイドの意向によって決まる部分は大きいですが。
’10年代のTVアニメ各年ベストを決めよう
2010年代ももう終わりに近づいているので、’10年代のTVシリーズのアニメ*1からベスト10を選ぶ恒例の企画をやろうと思いました。
その際、全期間全作の中から10作選ぶのではなく、各年でベスト1を1作品ずつ選出しようと決めていました。いわゆる「’10年代ベスト」といった言い方をしたときに、普通は前者の選び方をすると思うのですが、それだと重要作が多く出た年の作品に偏ったり、また、その人が一番アニメを見ていた時期のものの比重が高くなってしまう(もちろんそれもまた醍醐味とは言えますが)のではないかと思います。
どちらかというと、各年ごとに1作品ずつベストを出した方が、リアムタイムでの感覚が反映されて良いのではないかと考えました。後追いで見ることももちろんありますが、10年間を通してリアルタイムでシーンを追っていたことの蓄積というのはあると思います。
また、TVシリーズ作品に限る理由としては、その方がリアルタイム感が強く反映されるのと、劇場版の場合は「映画」として受け止められる側面も強いという都合によっています。
暫く前からTwitterで「#10年代アニメ各年ベスト10」のハッシュタグを作ってこの提案をやったところ、乗ってツイートをしたりブログを書いたりしてくれる人も多数いたので、まとまった段階でこちらで勝手に集計もしようかなと思っています。
(ハッシュタグの作り方が稚拙なせいで、「TV」を入れ忘れたり、「各年ベスト10」の「10」は紛らわしいのでは?と後から気付いたりしました。)
一応、「年をまたぐ場合は開始した年でカウントする」「続編になっているものは基本的には別作品扱い」くらいは考えていたのですが、特にレギュレーションもなしに緩い感じで始めたので、ざっくばらんな結果を出せればいいかなと思っています*2。
「そんなレギュレーションとか知らないし自分の基準で選んだベストなのだから数えてくれとも言っていない」と人によっては思われるだろうし、あくまで「こちらで勝手に」集計させていただく形にします……一応集計については真面目にします。
集計すると言っておいて何ですが、個々人のベストについて貴賤なくチェックしたいと考えており、特にブログで記事書いてくれる人がいたらその人のベストは気になるし読みたいな、と思います。
千葉集さんに記事を書いていただきました。どうもありがとうございます。
いっちさんに記事を書いていただきました。感謝いたします。
とりあえず、自分も各年ベストの10作品を決めました。
客観的な評価という観点もありますが、どちらかというと一人の視聴者としてどれだけ楽しんだかという視点での選出です。
________________________________
2010年 - 探偵オペラ ミルキィホームズ
第1話で結局4人がトイズを発動できないままに終わったというのがわりと衝撃で、これだと作品の前提が成立しなくなってしまうけどどうやって展開していくのか?という気持ちになったのですが、第12話まで溜めておいて、最後の対アルセーヌ戦でついにトイズ発動してからの怒涛のアクション炸裂でカタルシスを感じさせてくれました。
私的には、『ギャラクシーエンジェル』シリーズにハマって全話見たタイミングで本作を見ることができたので、ナンセンスギャグの似通ったテイストと、「G4」でのギャラクシーエンジェル声優陣参戦もあり、スムーズな流れで『ミルキィ』シリーズにハマっていくことができました。
頭身低めのキャラがデフォルメされた表情で金田調にぐりぐり動く、沼田誠也さんの作画テイストが全編に行き渡っているような感じが凄く快感でした。中野英明演出回の異様なテンション、吉原達矢作監回の破壊的なギャグ作画表現も忘れがたい。
この前久々に人と一緒に最終話だけ見返す機会があったけれど記憶していたより何倍も意味不明でボコボコしたアニメで笑ってしまった。
『ウテナ』以後のJ.C.STAFF作品を支えて来た巨匠の美術監督小林七郎さんは本作が実質的な引退作になり(4人が過ごす屋根裏部屋の時代がかった汚さも素晴らしかった)、手描きで背景美術を手掛ける主要スタジオだった小林プロが解散したことで時代としても一区切り着いた感じになりました。
『ミルキィ』シリーズはその後、2016年の劇場版でひと段落着いたところで桜井弘明監督にバトンタッチし、大晦日特番の形で散発的に続編が作られましたが、アイドルユニットのミルキィホームズ解散と共に2019年には終わりを迎えました。'10年代は『ミルキィ』シリーズに始まり『ミルキィ』シリーズに終わったと言っていいでしょう。
2011年 - 放浪息子
「志村貴子作品のキャラが志村貴子っぽい塗りで動いている!」と第1話にして全アニメファンの度肝を抜いた本作ですが、ロケハンで撮影した実写の写真を加工したレイアウトに、撮影段階でボカシやハイライトの処理を付けて水彩っぽい塗りを表現、更に被写界深度の演出を付けて見せたいものを際立たせることで画面を制御しており、全11話のシリーズでこれを最後まで破綻なく作れたのは凄過ぎると言わざるを得ません。

アニメにおいて、「実写ベースの細密なレイアウト」と「撮影段階でのルックのコントロール」の両者はともに'10年代を通して深化していったテーマだと言えますが、本作は2011年にして既にその到達点に立っていたのでは?という気もします。
第1話で二鳥くんがトイレで女装に着替えて出て来るとこで、トイレから出て来てサッと走り去っていく二鳥くんが女子トイレの標識の前を通るのをカメラが映しており、実際には男子トイレから出て来たことが分かると同時に、「男子→女子」への転身を視覚的に鮮やかに表現しており、そのカットで心鷲掴みにされた記憶があります。
(個人的には志村貴子さんの漫画は、時間的飛躍のあるコマ割りと、キャラクターの入り混じる群像劇の要素によって微妙に読みづらいと感じているので、『青い花』や『放浪息子』のように、優秀な演出家により映像化され整理されるとより一層好きになるパターンがあります。)
たまに断片的に見返すことがあるのですが、放映当時より魅力が色褪せない作品の一つです。

原作の中学生編のエピソードをノイタミナの放映枠全11話に合わせ再構成しており、第1話が二鳥くんのカメラ目線の独白というやや実験的な描写で始まり、それから第3話までかけて独白を交え二鳥、高槻よしの、千葉さおりの三人それぞれの関係性を表現し、整理した上で本筋の話に入っていくのも良かった。
あまり岡田麿里作品というイメージなかったのですが、そういえば『あの花』('11)もこれも『ブラック★ロックシューター』('12)も岡田麿里全話脚本で、この時期の岡田さんのノリにノッてる感すごい。
本作で演出として参加したイシグロキョウヘイさんは後にノイタミナで『四月は君の噓』を監督、撮影監督を担った加藤友宜さんはTROYCAの設立後『やがて君になる』を手掛けました。
2012年 - 戦国コレクション
前年に放映された『戦国乙女~桃色パラドックス~』('11)は現代の女子学生が戦国世界に転生する話であったと記憶しているのですが、同じくゲーム原作枠の『戦国コレクション』は総勢20人以上の女体化戦国武将が架空の戦国世界から現代にやって来て、各話数において戦国武将の現代での生き方を描いたオムニバス形式の作品でした。
やはりほぼ全話を映画パロで構成したサブカル的な趣向が話題になりますが、ふだん美少女アニメではあまり触れられないような泥臭い題材や市井の人たちにクローズアップした回も多く、各話シナリオの妙なアベレージの高さを含めて、’10年代の『セラフィムコール』('99)と評するに相応しい作品でありました。
『スティング』回は元ネタの流れをなぞりつつ小技の効いた脚本で楽しませてくれたり、『バグダッド・カフェ』の回は元になった映画は個人的に全然好きじゃないのにこれは良アレンジであったりと、何かと思い出深い作品です。大谷吉継の回だけヨーロッパが舞台で、BGMなしで表現主義的な背景の異色回ながら出色の感動作であったのも印象的です。原作ゲームのグラフィックを素朴なタッチにリファインした柴田勝紀さんのキャラデザインも良かった。基本的に1話完結や前後篇2話のエピソードが多いので、一つ一つを抜き出せば小さくまとまっている面はあるのですが、各話エピソードの充実さという意味では'10年代アニメの中でも随一のものだったと思います。
2013年 - 琴浦さん

例え安易であると言われようが、心を読めてしまう能力を持って生まれた琴浦さんがそれが故に友人と決裂し家庭不和を起こし母親に見捨てられ精神崩壊していく様を描いた第1話Aパートは衝撃であり、あなた達はアニメでこういうのが見たかったのだろう、と突き付けられる感覚がありました。AパートからBパートでガラリと流れが変わるのが快感なのですが、第1話の絵コンテには色調の指定もしてあったのをやたらはっきりと覚えています。
しかし、以上のパートもあくまで物語の前座として最大限の演出効果を狙ったが上のアレンジであり、本筋においては、そうしたバッググラウンドを背負った琴浦さんが真鍋くんやESP研メンバーとの交流を通し人間不信を解消していき、母親とのすれ違いにも決着を付けるまでを描いていたのが何より感動的であり、実直でウェルメイドなドラマを展開したラブコメとして本作は思い返されます。
アニメ終了続きが気になって原作読もうとしたら原作は絵柄全然違うし、しかもアニメはオリジナルの展開で最終話までやったので漫画で続きは読めないし、そのためアニメの二期もあまり望めないと知りちょっとした目眩を覚えたのを記憶しています。
本作のことは純化された美しい記憶になっているのですが、正直なところ今見たら全然違う印象持つかもしれなくて一番見返すのが怖い作品でもあります。
2014年 - ソードアート・オンラインII
SAOの第1期は放映当時は真面目に見ていなくて後追いで全話見てハマったので、SAOは第2期からリアルタイムで見ることになり、何だかんだこれまでで一番楽しんで見ていたシリーズだったなと思います。
銃撃戦をフィーチャーした新機軸の「ファントム・バレット」編~外伝的な位置付けの「マザーズ・ロザリオ」編までを映像化したシリーズで、その充実さにおいてもピカイチですし、取り分けラストを飾る「マザーズ・ロザリオ」編はSAOシリーズの懐の深さを感じさせ、ここまで追って来て良かったなと思わせてくれました。
数多のアクションシークエンスを始め、第13話のトラウマシーンといった竹内哲也さんの八面六臂の活躍も印象深いです。佐藤信子さん(長井龍雪さんの変名?)が手掛けた、シノンをフィーチャーしたリリカルなED1も良かった。
現在放映中の『アリシゼーション』まで追っているのですが、'10年代を通じて現在80話くらいまで展開していると知り驚かされます。それにしても、SAOはいわゆる「俺TUEEE系」の筆頭として挙げられることが多いですが(確かに願望充足型のファンタジーであることは事実ですが)、それでもレベルアップしていくまでの過程においては不能感を味あわされることも多く、劇場版の『オーディナル・スケール』でもARでの戦闘を強いられそれまでのプライドが折られる展開があるのであって、そういう語られ方をすることには未だにあまり納得が行っていません。
2015年 - 六花の勇者
ライトノベル原作のハイファンタジー作品ですが、このタイトルと題材でハードコア版『11人いる!』をやるとは思ってなかったので新鮮だったのと、魔族を倒す以前の、7人の勇者間の腹の探り合いだけでほとんど全話使ってしまうストイックさは全面的に買いたいと思いました。
7人全員が結界で森に閉じ込められたという舞台設定で、会話主体の密室劇を展開しながら常にアクションを伴わせて飽きさせない作りになっていました。
(高橋丈夫監督が直近の『女子高生の無駄づかい』に至るまで多用している)回り込み、スライド、旋回とやたら動く立体的なカメラワークを心理戦のストーリーテリングに活かしていくのも良かったです(多用し過ぎて終盤になって目に見えて体力なくなって来ているのも少し面白い)。フレミー役の悠木碧さんも好演を見せ、その圧倒的に陰を背負ったそのヒロイン像を醸成していました。
ただ、第12話までかけて謎解きのカタルシスを味あわせてくれたのは良かったのですが、最終話の終盤でいきなり次の章に向けた新しい展開が入って来たことでストーリーも仕切り直しになり、典型的な「俺たちの戦いはこれから」ENDを迎えたことで凄まじい脱力感を覚えたのは事実です。
ですが、それまでの話数はかなり楽しんで鑑賞していたのは事実であり、オチがどのようなものであってもその過程まではなくならないと考えるので、本作についてはやはり評価したいと考えます。
'10年代のアニメは1クールものが増えたことで、原作数巻分の展開をギュッと圧縮して映像化するシリーズ構成の技術が培われましたが、この作品のようにライトノベル第1巻の内容を1クールかけて緻密にやった例はそれほど見当たらず、そうした意味でも稀有な作品です。
2016年 - Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-
第1話で一挙に10人前後の人物を主役として登場させ、リアルタイムで進行する出来事についてザッピング形式で視点を切り替えていくストーリーであることが示され(新城カズマの『15×24』っぽい)、これで本当に1クールでまとめ切れるのか不安になったのですが、そうした懸念が完全に杞憂であったことが分かり印象に残っている作品です。
本作に脚本として参加している高木登さんがシリーズ構成をやった『デュラララ!!』シリーズ等であれば、サブエピソードも交え2クールや3クールで展開したであろうストーリーを、高速早回し台詞とグルーヴ感ある圧縮展開で強引に12話にまとめたことでかなり面白いことになっており、また、それでありながらアイテムや設定、伏線も中途半端にせず総勢10人のメインキャラ全員についてちゃんとオチを付けてまとめた切った手腕にはひたすら脱帽させられました。
主人公は妄想科学シリーズによく出るタイプのこじらせたオタク像といった感じですが、森塚駿のキャラクターはナチュラルに志倉千代丸さん感あって好きです。
最終話でも例を見ない長回し的手法がありましたが、神戸守さんがやった第5話や、それに続く第6話、第7話、同じく神戸さんの第10話などはひたすらアバンギャルドな見せ方に酔いしれました。演出的にも2016年で一番尖っていた作品は、『Re:ゼロ』と並んで本作であったようにも思います。
2017年 - プリンセス・プリンシパル
「きらら版『ジョーカー・ゲーム』」の前評判*3や、物語途中のエピソードから始まる第1話があまりピンと来なかったので少し敬遠していたのですが、入れ替わりスパイ作戦でサスペンスを展開する第2話からぐいぐいとハマっていき、写し鏡のような「二人のプリンセス」を巡る顛末が語られる第8話の百合で一気にテンションが最高潮まで高まり、1ファンとして作品の虜となるに至りました。
ちせをフィーチャーした第5話も、江畑さんの展開する剣戟アクションと相まって名回と名高いですが、暗号表奪取のため連絡員の死体をモルグから探し出す作戦に絡めてドロシーと父親をめぐる悲劇をやった第6話も個人的に忘れがたいサブエピソードでした。洗練された台詞回しも快く大河内一楼さんの脚本に惚れ直した作品でもあります。王国の状況を鑑みれば展開的にまだ語り残している点の多い終わり方ですが、自分などはとにかくキャラクターを見たいという側であったのでそれでもオールオッケーな部分がありました。続編も待たれます。
2018年 - ダーリン・イン・ザ・フランキス
2018年は支持を集めるオリジナルアニメが何作もあった年ですが、個人的には『ゾンビランドサガ』や『SSSS.GRIDMAN』のノリにいまいちハマることが出来ず、瞬間最大風速ではかなり良かったはずの『ダーリン・イン・ザ・フランキス』や『レヴュースタァライト』の結末にも予定調和感や脱力感を覚えてしまい、『宇宙よりも遠い場所』は客観的に見てかなり完成度の高い作品であるとは思いつつも、年間ベストに挙げるほど好きかと言われるとそうでもなかったため、苦慮した年ではありました。
『ダーリン・イン・ザ・フランキス』はその中にあっても視聴中とても楽しんで見ていたと感じています。当初は旧ガイナックス作品の意匠を多分に取り込んだ設定や、性的なニュアンスに若干たじろいていたのですが、群像劇については描きたいものがストレートに伝わって来るところもあり、世界設定についても興味を持って鑑賞できました。
TRIGGER×A-1の豪華スタッフ一点投入で、高雄統子さんが演出処理まで担当し照明芸が冴え渡る第5話など年間ベスト級の話数はいくつもありました。
第20話前後から核心の設定に当たる侵略者VIRMの話が入って来て、それまで積み上がって来た群像劇の内容が寸断されたような感触があり、最終話までの展開を見てもどこか取って付けたようなまとめ方になっており不満足な点は残るのですが、リアルタイムで見ていて最も楽しんでいたのは本作であるのは事実です。
2019年 - 約束のネバーランド
とにもかくにも神戸守監督にこのような適任の題材(しかもジャンプ原作のメジャー枠)を振ってもらえてありがとうございます、とプロデューサー各位に感謝の意を表したい作品でした。『Occultic;Nine』もそうですが、アニメでガチガチのホラーやサスペンスをやっている作品って意外とあまりないので、こういう題材が、それを上手くやれる人の元に届くことは望外の喜びです。窃視のようなカメラ位置を選択しいつ見つかるか分からないスリルを味あわせたりと、常に緊張感を出すための仕掛けが用意されていて間延びすることを知らないシリーズでした。POVのトラックショットや、じりじりと三次元方向に動かすカメラなど、3Dの恩恵を受けた演出も多く散見されました。第7話などを見るにつき、神戸さんはいまだに新たな見せ方を開発していっているのだなと思わされます。
シスタークローネが自室で話しかけている人形はアニメオリジナルのようなのですが、あの人形は台詞では全く言及されていなくて、ただシスターの一人語りを誘い不気味さを醸し出すためのみに使われており極めて映像言語的な使い方でした。神戸監督のOVA『電波的な彼女』でもやたら執拗に人形を映しているし、人形のああいった使い方は好きなのかな?と思います。
________________________________
まとめ
こうして見ると、意外とあまり迷わなかったなと思います(2012年は『ココロコネクト』、『ブラック★ロックシューター』と若干迷いました)。選んだ作品のリストを振り返ってみると、特に後半にかけてはA-1/CloverWorksが手掛ける大作の割合が高くなり、これはアニメ業界の再編成の流れもあるかもしれませんが、自分の好みが大衆的なものになってあまり捻くれなくなって来ているのかなと感じました。
また、サスペンスやホラーをやっているようなシリーズに惹かれる面もあり、優秀な演出家やスタッフの手により翻弄されたいという潜在的な欲求もあるように思います。
各年ごとに1シリーズという縛りで選んでみると色々と発見もあり面白かったので、アニメファンの人は余裕があって気が向いたらやってみることをお勧めします。
キング・ヴィダー『群衆』(1928)
アニメとはほぼ全く関係ない話題ですが、『群衆』の話をしようと思います。
※この記事は作品についての全面的なネタバレを含みます。

格安DVDで見たら、パッケージ裏の解説文が本編を1秒も見ていなくても書ける内容しか書いてなくて面白かったです。
1928年のアメリカ映画ということで、ちょうどサイレントからトーキー(発声映画)の端境期にあたる時期に公開されたサイレント作品。ゴダールが言及していたり、「映画ベストセレクション」的なやつにも入ったりもしておりそこそこ著名な作だと思います。
原題はそのまま『The Crowd(群衆)』で、古典に相応しい、シンプルなテーマを感じさせるタイトルと言えるでしょう。
導入:
1900年7月4日、合衆国の124回目の独立記念日という特別な日にその男の子は生まれました。「この子はきっと大物になる」「多くの機会を与えよう」と父親は決めました。
その父親は男の子が12歳のときに亡くなりましたが、その遺志を継ぐことによってよってますます、「大物になる」という少年の意志は強くなりました。
21歳になったとき、青年になった男の子、ジョン・シムズは機会を求めて人口700万が集う大都会・ニューヨークに乗り出しました。
大物になるためには、群衆に飲み込まれない傑出した存在にならなくてはならない……
少年期の主人公が父親の死を告げられるシーンは、1分きっかりの長回しで撮られており(父親の亡骸が階段を通ってから、少年がその階段を上がって来るまで)、サイレントで長回しというのはその間インタータイトルが全く入らない(つまり実質的にも台詞なし)ということなので、なかなか根性が要りそうな試みです。
映画の全体通して、随所でカットを割らずに芝居をさせることによって、登場人物の感情を途切れさせないようにしようとする工夫が見られます。

その後、 21歳になってニューヨーク行きの船に乗ってやって来る主人公。

この時のショットは絵に描いたような「都会に夢見て上京して来る若者」の図になっていて笑ってしまいます。カメラが重い時期のサイレント映画は、一枚絵の構図で簡潔に物事を表現することが要請されることから、しばしば漫画のコマみたいな画になっていると思う。ちなみに右側の人はこれ以降のシーンで全く出て来ません。
ニューヨークに到着してからのシーンでは、人々の行きかいや車の往来が多重露光によるモンタージュで表現されています。このシークエンスはちょっと長いですが、大都会NYの目のくらむような圧倒的な群衆を、その猥雑さを込みで効果的に表現しています。若干ソ連映画っぽいですが、『カメラを持った男』('29)より前なんですね。


そして、大都会を映すシークエンスから、その中での主人公の姿に滑らかに遷移していきます。

(ミニチュアの)摩天楼の側面をなめるように映し、窓ガラスを抜けて室内に入っていくカメラワーク、ここもかなり現代的な発想で驚いた。

NYに定住し始めた主人公は保険会社の事務社員の一人として雇用されています。


ナンバリングを振られている多人数の労働者、官僚的手続きを思わせる書類の事務作業、個性を感じさせない規則的な並びのデスクなど、ここを取り出すとなかなかにディストピアっぽい絵になっています。
同じデスクと作業者が一様に延々と並んでいるオフィスなど、本作での群衆を見せる演出はオーソン・ウェルズの『審判』('62)にも影響を与えたとされています。


定時になった瞬間に皆一斉に帰るところも両作ともに同じですね。


『審判』のビジュアルが後のディストピアSFに影響を与えていることも考えると、『群衆』の映画史における意義も一層感じられるようになると思います。
また、それに続く、職場に併設されている洗面所のシーン。

多人数が往還する通路を合わせ鏡の洗面所にすることで、人の波が無限に続いていくような印象を与えています。通常の劇映画ながら、群衆を演出するにあたっては大胆に表現主義的な手法を採用しています。
また、映画の後半のシーンで、ビーチにてバカンスを楽しむシムズの家族(主人公が妻子をもうけた後)。


ビーチで主人公が楽器を鳴らして歌っていると、横で昼寝をしている老紳士に叱責を受けるのですが、この会話シーンの両者のカットでは一方が主人公のシングルショットですが、もう一方はビーチにびっしりと埋まった群衆のショットです。
このビーチのシーンの前半では、シムズら家族4人が映っているカットでは徹底して4人以外が映らないように撮られていますが、先行するビーチの群衆のショットによって、フレーム外にいても、 そこには常に群衆がひしめいていることが示唆されています(実際の都市生活者にとってそうであるように)。


先ほどのシムズのショットと、ビーチに埋まった群衆のショットとは古典的な切り返しのモンタージュで繋がれていましたが、この切り返しによって、家族の団らんであってもそれは絶えず群衆と隣り合わせであるという事実が浮かび上がってきます。こうした、大胆な画の切り替え(単数⇔複数)は、サイレント期の映画ならではですね。
少し展開を先に進め過ぎました。
続きのあらすじ:
保険会社で働き始めたシムズは、同僚のバートに誘われたダブルデートで
知り合った女性と結婚し、二人の子供をもうけます。当初は先行きが明るく、周囲の凡人を馬鹿にしていたシムズでしたが、
そこから5年経っても同僚と比べてなかなか昇進できませんでした。シムズの尊大な態度と実際の境遇との間にはだんだんと開きが生じてきて、それが妻との不仲にも繋がっていきます。
そんな折、広告のキャッチコピーのキャンペーンに応募していたシムズは
自身のコピーが採用され、幸運にも賞金の500ドルを獲得します。歓喜する二人は、子供たちにすぐに帰って来るよう伝えますが、
急いで帰って来た娘はそこで交通事故に遭ってしまう……
まずは結婚して間もなくのシーンから。
夫からの小言の多さ、あまりのクズっぷりに耐えられなくなり離婚を決意した妻が、主人公を見送った後に、葛藤の果てにやはり翻意するまでの感情芝居。ここは1分10秒きっかりの長回しで捉えられています。


この時の夫に向ける想いの複雑さ、葛藤を表すと同時に、この後妊娠したことを夫に告げるので、それを引き立てる溜めの意味もあるでしょう。
その後、妻の出産を仕事先で知って主人公が駆けつけるシーンも見どころ(ここでまた、病院で妻を待つ多人数の夫たちに出合わせ、自分の子と妻を見つけ出せるのか?とサスペンスになるのも面白い)。
看護師に案内され、扉を開けて病棟にゆっくりと入っていく主人公。カメラは主人公の背中に貼りつきゆっくりとドリー・インし、主人公と一緒に入っていきます。ここは看護師に案内されてから病棟内で妻を見つけるまでを、カットを割らずに40秒ほどの長回しで捉えています。


ヒッチコック『バルカン超特急』('38)のラストとかもそうですが、こうやって、内側にあるものに対して期待を持っている人物と一緒にカメラが扉の中に入っていくカットって不思議とカタルシスがありますね。ここでベッドの配置が三角形の構図になっているのも効果的で、主人公の期待の高まりを上手く演出しています。
娘が交通事故に遭う悲劇的なシーンでは、野次馬として蟻のように群がってくる群衆のイメージが、やはり鮮烈な構図で目に焼き付きます。


『卒業』('67)のラストシーン、大喝采の逃避行を遂げた若い二人が乗り込んだバスで、その乗客が全員年の行ったおじさんおばさんで、皆で一斉にこっちを無表情で見ているのが映るカットにぞっとさせられた記憶があるのですが、この映画における群衆もどこかそういった、意志を持たない酷薄な印象を持っています。
続きのあらすじ:
娘を失った悲しみに沈む主人公たちに対しても、社会の荒波は容赦なく襲いかかります。
仕事に身が入らなくなり叱責を受けた主人公は、昇進の望めない仕事に見切りをつけ退職を決意しますが、残っている仕事口は、プライドの高い主人公には耐えられない仕事ばかりでした。
転職を繰り返すうちに、妻に愛想を尽かされるようになり、主人公は徐々に追い詰められていく……
群衆を忌避し、軽蔑していた青年が社会の荒波に揉まれるうちにやがて群衆に埋没していく悲哀。何者かになろうとして何者にもなれず、夢を失っていく悲しみ。この映画はそれを丹念に描いていきます。
しかし、単に群衆の非情さに呑まれて主人公が夢破れ落ちぶれていくというドラマであればそれは陳腐な構図であり、後のアメリカ映画においても繰り返されたものと同じです。そこに夫婦の問題を密接に絡ませて、最後には家族との復縁と同時に主人公の復帰を一遍に表現するストーリーテリングがこの映画を特別なものにしていると思います(同時に、家族との間に残った絆が救いになるというのはやや保守的な価値観であるかもしれません)。
そして、この映画において最も感動的なシーンは、まさにそのラストカットに他なりません。
ラストシーンについて
もはや古典も古典なので問題ないだろうと思いネタバレをしてしまいますが、この映画の白眉であるラストのカメラワークについてです。このラストによって、本作における「群衆」の意味合いが全く変わって来るという仕掛けになっています。

挫折しきった主人公はそこからの復帰を成し遂げ、最後に家族三人で連れだってヴォードヴィルのショーを鑑賞しに劇場にやってきます。
妻と夫も和解し、主人公も見つけた仕事に対し前向きな姿勢を抱くようになり、三人とも屈託なく笑いながらショーを楽しめるようになっています。
そこでカットが切り替わり、この映画のラスト数ショットに移っていきます。客席に座る彼ら三人の姿からカメラがどんどんクレーンショットで引いていって(遠ざかっていき)、ショーを笑って鑑賞している群衆が俯瞰で画面一杯に映されます。
三人の姿はどんどん小さくなっていき、ついには群衆の笑いの一部に溶け込んでいきます。一人一人が点のように小さく映るようになった真俯瞰のショットで映画は締めくくられます。
ここに至って、主人公の姿は初めて、群衆と分かたれた個の存在ではなく、その一部へと溶け込んでいきます。そしてそれは群衆に圧倒され、呑まれてしまうといったものではなく、笑い合う群衆の中に、自身もまた成員として復帰するという希望も感じられるものになっています。
それまで一貫して、主人公に対する脅威として演出されて来た「群衆」が、ここにきて主人公にとっての見通しが晴れたことで一気に魅力的なものになり、そこに主人公もまた溶け込んでいく!というカタルシスも充溢しています。
また、映画内でこれまで、喜怒哀楽をもって描かれて来たドラマを背負った主人公たちの姿が、群衆に溶け込んでいくことで、群衆の誰もがみな、そのようなドラマをそれぞれに背負い得る存在であるという気付きにも繋がっていきます。
普通じゃない人間になろうとした、普通の人間という主人公のストーリーは、彼が群衆の中の一人(one of them)として溶け合っていくことで群衆全体のドラマへと膨らんでいきます。群衆の皆が皆、かつて普通じゃない人間になろうとしていた普通の存在だった、というとても残酷なメッセージとも取れますが、それは逆に希望でもあります。たとえ平凡な存在であってもそれぞれの激しいドラマを背負って生きており、そしてその人生は価値があるということになるからです。個々のそうした人たちで構成され、 皆で笑い合っている群衆に、多幸感すら感じられるようになるのが素晴らしい部分です。
また、この象徴的なショットが、映画内での劇場で撮られているというのも見過ごせません(別に『Air/まごころを、君に』ではないですが、当時映画館でこの映画を見た人はちょっとした錯覚に陥ったのではないでしょうか)。
ここにおいて、まさにこの映画全体のストーリーが、映画館にこの映画を見に来ている観客それぞれのものに重なってきています。
この映画において描かれたドラマは劇中でのキャラクターにとってだけでなく、この映画を観に来ている人たちそれぞれのドラマでもあるという事実がここで浮かび上がってきます。 この映画を見て身を重ねたり、共感したり、軽蔑していた者もそれぞれに群衆を構成する一員であるという事実を、この映画は突き付けてきます。多分、このことを受け入れられるかどうかが、その人の中でのこの映画の評価を二分することになるのではないかと思います。
まさに、普通の人々を描いた、『群衆』の名を冠するに相応しい映画であると言えるでしょう。
大戦後まもなくの貧困に喘ぐイタリアにおいて制作された『自転車泥棒』('48)が、当時の社会的な状況のみならず現実の不条理さやどうにもならなさを伝えているように、大恐慌時代を前にしたアメリカで公開された『群衆』も、我々が直面する現実についての普遍的な事実を伝えています。
また、テーマパークでのデートに始まり、妻との離別、サイレントでありながら音楽に合わせての復縁など、メロドラマとしても一級品の作品になっており、サイレント期を支えた演出家の底力を感じさせられる映画でした。
既存のDVDだと画質がめちゃくちゃ悪いので他のヴィダー作品と一緒にHDリマスター版のソフトとか出ないかな…と思います。
映画『空の青さを知る人よ』(2019)雑感
・ファーストショット、画と言うよりくしゃみの「音」から映画が始まる(くしゃみのアップから全身のロングへの切り替え)。目を閉じてのベースの演奏に入れ込ませて他キャラの動作(ドアの開閉ショット等)、過去の回想カット、と音で繋いでいく(ライブシーンから木魚の切り替えの衝撃性)。現在に囚われず異なる時間軸、場所のカットが切り替わっていく、しっちゃかめっちゃかな編集(ここまでやるのは『トレイン・ミッション』以来?)
しかしそれらは主人公にとっての意味を持つもので、意識の流れによるものだというのが浮かび上がって来る。主人公がイヤホンジャックを外し、外部の音が入って来るタイミングでそのことが決定的になる。アバンタイトルの終わりにおいて、空のショットにカメラが上がり、『空の青さを知る人よ』のタイトル。
このアバンタイトルによって主人公のバックグランドを説明し、映画全体の象徴ともいえるシークエンスになっている。ここでまず100点!という感じなのだが、このアバンタイトルの使い方は新海誠を感じさせる(というか『君の名は。』)。
(というのも、新海誠の直近二作においては、冒頭のアバンタイトルにおいて映画の後の方のシーンを先取りして出しているんだけれど、このシーンってモノローグでも映像でも、ほとんど後のシーンを見れば分かるようなことしか言っていないので、本編の象徴や、予告編のような映像になっている。)
全体的にクライマックスでの走りや上昇、降下といった運動の取り入れ方など新海誠エッセンスを感じさせる映画だった。長井龍雪さんと新海誠さんは良い意味で触発し合っているのが伝わって来る。
・演出的には、室内を映す際に広角レンズのレイアウトを選択し、カメラが壁をぶち抜かないようなリアルなカメラ位置。
会話シーンでレイアウトに凝る。敷居を活用して区切った空間にキャラクターを配置することで意味性を持たせている。主人公の伸びやかでフェチを感じさせる芝居。特に脚部の自然な動作を強調。
・岡田麿里さんは究極的には女性キャラの自意識にしか興味ないのでは?と思う。主人公の尖ったパーソナリティは良かった。修羅場を作ってそれに持って行くまでの手付きが個人的に好きなんだけど、今回はそこまでのあざとさや際どさはなくて抑制されていた。
ただ、しんのが最初に登場してそのことを主人公があか姉に伝えに行くシーンで、あか姉が作っているのがメンチカツで、ぐちゃぐちゃにかき混ぜている肉片が飛んで主人公の頬に付くシーンは最高。
(あと慎之介の追っかけをしていた女子高生は、結局それを口実にして主人公の方に近づきたかったようにしか見えなかったが、邪推だろうか。)
・最終的に慎之介としんのの男性キャラ二人は完全に蚊帳の外に置かれている(しんのの方もクライマックスになるまではずっと屋内で閉じ込められているし。)。結局のところ自身の夢の問題は自分で解決するしかないのだと思う。この題材であれば「慎之介が夢に向き合って立ち戻るまで」の過程に焦点化するストーリーになってもおかしくないのに、それをメインに据えずに、それを介して姉妹が互いに向ける想いとすれ違いを描いた作品になっている。そこがすごく現代的な様に思った。
・エンドロールで出て来る(その後を描いた)画は要らないという意見には全面的に同意するが、自分の場合どちらかというと「その後の話を自分たちで想像したかった」という理由。ただ、やはりそこまで作品内で描かないと気が済まない/そこまでやりたいというのが超平和バスターズの人たちなのだろうなと思う。

![私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 第1巻 [Blu-ray] 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 第1巻 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51TEhEac6fL._SL160_.jpg)
![六畳間の侵略者!? 第1巻 (初回限定版)(健速書下し小説同梱) [DVD] 六畳間の侵略者!? 第1巻 (初回限定版)(健速書下し小説同梱) [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Suyu-q0sL._SL160_.jpg)


![セラフィムコール 第三話「洋菓子の味」 [DVD] セラフィムコール 第三話「洋菓子の味」 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21658YBF1AL._SL160_.jpg)
![世界名作映画全集100 群衆 [DVD] 世界名作映画全集100 群衆 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41W5YGWPNZL._SL160_.jpg)
![群衆 [DVD] FRT-184 群衆 [DVD] FRT-184](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51i2HDfu4EL._SL160_.jpg)

